

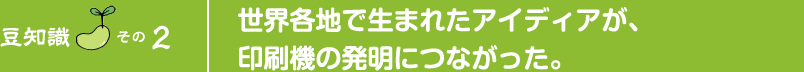
今の本のスタイルを思いついたのは古代ローマのジュリアス・シーザーでしたが、その時はアイディアだけで実現しませんでした。それに目をつけたのは中世になって、ヨーロッパの修道院(しゅうどういん)の僧たちが、聖書(せいしょ)を本にすることを思いつきました。しかし当時は印刷技術がなかったので、写本(しゃほん)といって、専門家(せんもんか)が自分たちの手で本を写していました。これは日本でも同じで、『源氏物語(げんじものがたり)』や『徒然草(つれづれぐさ)』などは、書き写した本を皆でまわし読みして、ベストセラーになったのです。
 ところで、今も使われている印刷技術のルーツは、ドイツのグーテンベルクによる活版印刷(かっぱんいんさつ)の発明です。それまで書き写さなければいけなかったので手間がかかっていましたが、印刷機の登場で短い時間でたくさんの情報を読者に伝える手段が生まれたのです。日本では安土桃山時代に、中世ヨーロッパのルネッサンスを唯一(ゆいいつ)目撃(もくげき)した日本人である天正遣欧少年使節団(てんしょうけんおうしょうねんしせつだん)が、ヨーロッパから持ち帰り、キリスト教布教のための教科書を印刷しましたが、禁教令(きんきょうれい)により印刷物の一部は歴史から姿を消しました。しかし、印刷技術が日本にもたらされたことが、その後の日本のコミュニケーション手段の主流となったのです。
ところで、今も使われている印刷技術のルーツは、ドイツのグーテンベルクによる活版印刷(かっぱんいんさつ)の発明です。それまで書き写さなければいけなかったので手間がかかっていましたが、印刷機の登場で短い時間でたくさんの情報を読者に伝える手段が生まれたのです。日本では安土桃山時代に、中世ヨーロッパのルネッサンスを唯一(ゆいいつ)目撃(もくげき)した日本人である天正遣欧少年使節団(てんしょうけんおうしょうねんしせつだん)が、ヨーロッパから持ち帰り、キリスト教布教のための教科書を印刷しましたが、禁教令(きんきょうれい)により印刷物の一部は歴史から姿を消しました。しかし、印刷技術が日本にもたらされたことが、その後の日本のコミュニケーション手段の主流となったのです。